保健だより<5>
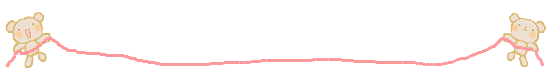 お子さんのくつのサイズあっていますか?
お子さんのくつのサイズあっていますか?
お子さんたちが靴をはく様子や外で遊んでいるとき、散歩に出かけたときなどに時々気になることってありませんか?
1.大きすぎると感じていませんか?
お子さんとだれかが一緒の散歩の時などは間を開け過ぎないようにして歩くので、前の人の靴を踏んでしまうこともあります。
大きめな靴だと少し踏まれただけで脱げてしまうことがあり、横断歩道の真ん中に靴だけが取り残されて・・・。といった経験、ありませんか?
靴が脱げて転び後ろにいた人も転んでしまうこともあり、一般道路で歩道の無いところを歩くようなときは危険です。
また、走ると脱げてしまうようでは思い切り走って遊ぶこともできません。
2.靴ひも式など、一人で履くことができない?
紐で調節するものでも横にファスナーが付いていて脱ぎ履きできるものなら大丈夫です。
ですが、紐がほどけてしまっても、一人で結ぶことができない、散歩の途中でしょっちゅうほどけて止まるなど、
遊びや生活に支障を来すような場合は、避けていただいた方が良いと思います。
履いてしまえばいいのですが非常に履きにくく時間がかかるものもありますね。
そこで、〜靴を選ぶときのポイント〜をお伝えします。
*つま先に適度な広さとある程度の高さがあり靴の中で指が動かせるもの
*歩くときに蹴りだしやすいように、つま先が少しそりあがっているもの
*足が固定できるようにかかとがしっかりしているもの
*指の付け根辺りで靴底が曲がるもの
*靴底は適度な硬さと弾力があるもの
*紐かマジックテープで甲の高さが調節できるもの
*靴の素材は通気性のよいもの
上記のような素材や形状のものをお選びいただくと、怪我もしにくく、子どもにとっても動きやすく快適さを感じられるものです。
活動量の多いお子さんにとって、靴はとても大事なグッズです。お母様がしっかり見て触れてお選びください。
そして、大人と一緒で、靴を買うときには必ず両足で履いて少し歩かせて見ましょう。
同じサイズでもメーカーやデザインで多少大きさが違うので、サイズだけで選ばず、必ず履かせてみてください。
また、購入後も、子どもは身長と同じく足のサイズも大人に比べるとどんどん大きくなります。
2〜3ヶ月に1度くらいは靴が合っているかどうか必ず見てあげてくださいね。
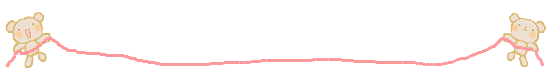 普段の生活で注意していただきたいこと
普段の生活で注意していただきたいこと
前髪が目にかかっていませんか?
目にかかると手でこすり、角膜を傷つけやすくなります。
6歳頃までは視覚が急激に発達する大切な時期です。髪は切るか結えるかして、毛先が目にかかったり入ったりしないようにしてあげてください。
肌の様子はどうですか?
着替えの時やお風呂の時に全身の様子を見てみましょう。ザラザラ・ガサガサ・ジクジク・ポツポツ
いつもと違ったところはありませんか?
正しい体温のはかり方、ご存じですか?
<脇の下で測るときは>
*脇の下の汗をよく拭いて
*脇の下の中央部に水銀部分を前方から差し込む
*体温計がずれないように子どもの腕をしっかりつけて押さえる
日によって多少の変動はあります。体温計によっても多少差があるので同じ物を使って下さい。
<耳で測るときは>
正しく測るにはきちんと鼓膜にセンサーを向けることが必要です(脳内温度に近いとされる鼓膜温を感知することで体の内部温度を測定するものです)
脳内温度は37〜38度あるので、鼓膜温を感知すると脇の下で測るより比較的高めになります。
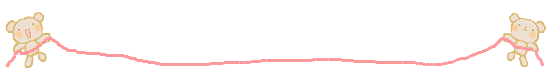 6月4日は虫歯予防デーでした。
6月4日は虫歯予防デーでした。
子どもの歯
生後5ヶ月ころから歯が生え始め、乳歯は20本生えます。5歳頃には乳歯が抜け永久歯が生えてくる子どももいます。
歯の生える時期、抜ける時期は個人差がとても大きいので、お子さんが一般的な成長過程をとらなくても、必要以上に心配しないように。
歯の役割
一番の役割は食べることです。鋭い前歯で食べ物をかみ切り、うす状の奥歯で砕いたりすりつぶしたりして栄養を身体に取り組みやすくします。
子どもの歯には食べることの他にもいくつかの大切な役割があります。声帯で発した原音を舌や上顎・歯・唇などを使ってはっきりした
音声に作り変え、言葉を正しく発音することやよく噛むことによってあごの成長を促したり顔の形や姿勢を整えるなど、子どもの
発育に深く関わっています。
虫歯って
虫歯は歯・食べ物・虫歯菌の3要素に時間の経過が加わった時にできてしまうものです。口の中に食べ物のカスが残っていると、虫歯菌は
その糖分を分解し、ねばねばした物質を作って歯の表面に張り付きます。これが歯垢(プラーク)です。虫歯菌は歯垢に住み着き、
さらに他の糖がやってくるとこれを取り込み分解して酸に変えます。この酸が歯を溶かし虫歯になります。歯の質は生まれ持ったものです。
食事や間食の時間を決めて食後は口をゆすいだり歯みがきをして口の中に食べ物を残さないようにしましょう。
カルシウムが大切です
保健だより<1>はこちらから
保健だより<2>はこちらから
保健だより<3>はこちらから
保健だより<4>はこちらから
 <?>
<?>
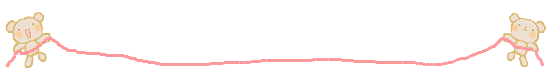 お子さんのくつのサイズあっていますか?
お子さんのくつのサイズあっていますか?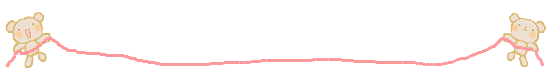 お子さんのくつのサイズあっていますか?
お子さんのくつのサイズあっていますか?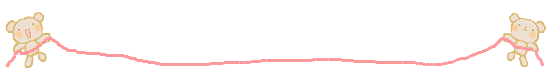 普段の生活で注意していただきたいこと
普段の生活で注意していただきたいこと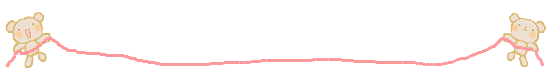 6月4日は虫歯予防デーでした。
6月4日は虫歯予防デーでした。 <?>
<?>